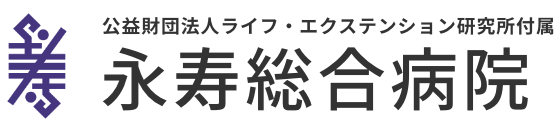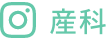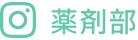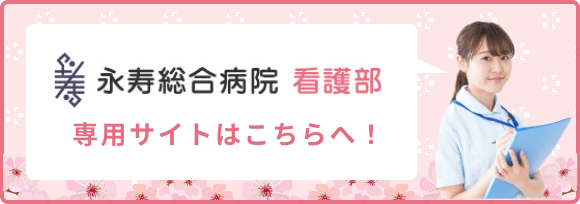gooDrug『インフルエンザ流行期到来!』
インフルエンザ流行期到来!
インフルエンザの症状とその対策
昨年12月に、5年ぶりに都の警報基準を超え、インフルエンザA型の流行が拡大。
年末年始の救急診療には多くのインフルエンザの患者さんが受診されました。
2月に入り、暦の上では立春に入りましたが、むしろ寒さは本格化し、体調を崩される方も多いのではないでしょうか?
インフルエンザB型の患者数も増加してきており、例年より流行期が早く来て、連続感染するリスクも高まっています。
インフルエンザにかからない、感染を広げないために、対策をしていきましょう!
主な症状
- 38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等が急激に現れることが特徴
- のどの痛み、鼻汁、咳等が現れることもある
- 風邪よりも、強い倦怠感などの全身症状がおこりやすい
対策例
- こまめな手洗い、消毒
- マスクの着用(人混みに行く時や会話をする時、咳・くしゃみが出る時等)
- 適度な室内加湿・換気
全く症状のない(不顕性感染)例や、感冒様症状のみで、感染していることを本人も周囲も気が付かない軽症の
例も少なくありません。
そのため、上記の感染対策は日頃から心掛ける必要があり、また、正しい方法で行うことが重要です。
皆さんは、正しい手洗いできていますか?
東京都のホームページにも掲載されていますので、しっかりマスターしましょう!
また、万が一感染した場合には、感染を広げないことも大切です。
早めに医療機関を受診し、回復に努めましょう。
いわゆる咳エチケットを実施する、外出を控えるなどの行動も大切です。
年度末が近づき、忙しくなる時期こそ、十分な休養やバランスのとれた栄養摂取で体調管理に気を配りましょう。
インフルエンザ治療薬について
予防していても、インフルエンザにかかってしまったという時に処方される代表的な治療薬の種類やはたらき、特徴についてご紹介します。
オセルタミビル(タミフル®)
もっとも多く使用されているインフルエンザ治療薬です。
用法は腎機能によりますが、通常1日2回5日間の服用で、カプセルとドライシロップの剤形があり、0歳から服用できるのが特徴です。
ザナミビル(リレンザ®)
吸入タイプの治療薬です。
1日2回5日間の吸入が必要です。
喘息など呼吸器系の基礎疾患がある方には推奨されません。
ラニナミビル(イナビル®)
吸入タイプの治療薬です。
1度の吸入で治療が完結することが特徴です。
ザナミビル同様、喘息など呼吸器系の基礎疾患がある方には推奨されません。
ペラミビル(ラピアクタ®)
インフルエンザ治療薬の中で唯一の点滴薬です。
重症化した場合や肺炎を合併した場合、または経口投与も吸入も困難な場合に使用されます。
バロキサビル マルボキシル(ゾフルーザ®)
2018年に承認された比較的新しいインフルエンザ治療薬です。
1度の服用で治療が完結することが特徴です。
発売当初から耐性ウイルスの発現が問題となっていましたが、その後の研究で耐性ウイルスの発現割合は年齢との関連があると示唆されました。
そのため、12歳未満の小児には慎重な適応判断が必要とされる薬です。
インフルエンザ治療薬服用の適切な時期とは?
インフルエンザ治療薬の効果は、症状が出始めてからの時間や病状により異なります。
インフルエンザ治療薬の投与は全ての患者に対しては必須ではないため、使用する・しないは医師の慎重な判断に基づきます。
また、インフルエンザ治療薬の服用を適切な時期(発症から48時間以内)に開始すると、発熱期間は通常1~2日間短縮され、鼻やのどからのウイルス排出量も減少しますが、症状が出てから2日(48時間)以降に服用を開始した場合、十分な効果は期待できません。
使用する際には用法、用量、期間(服用する日数)を守ることが重要です。
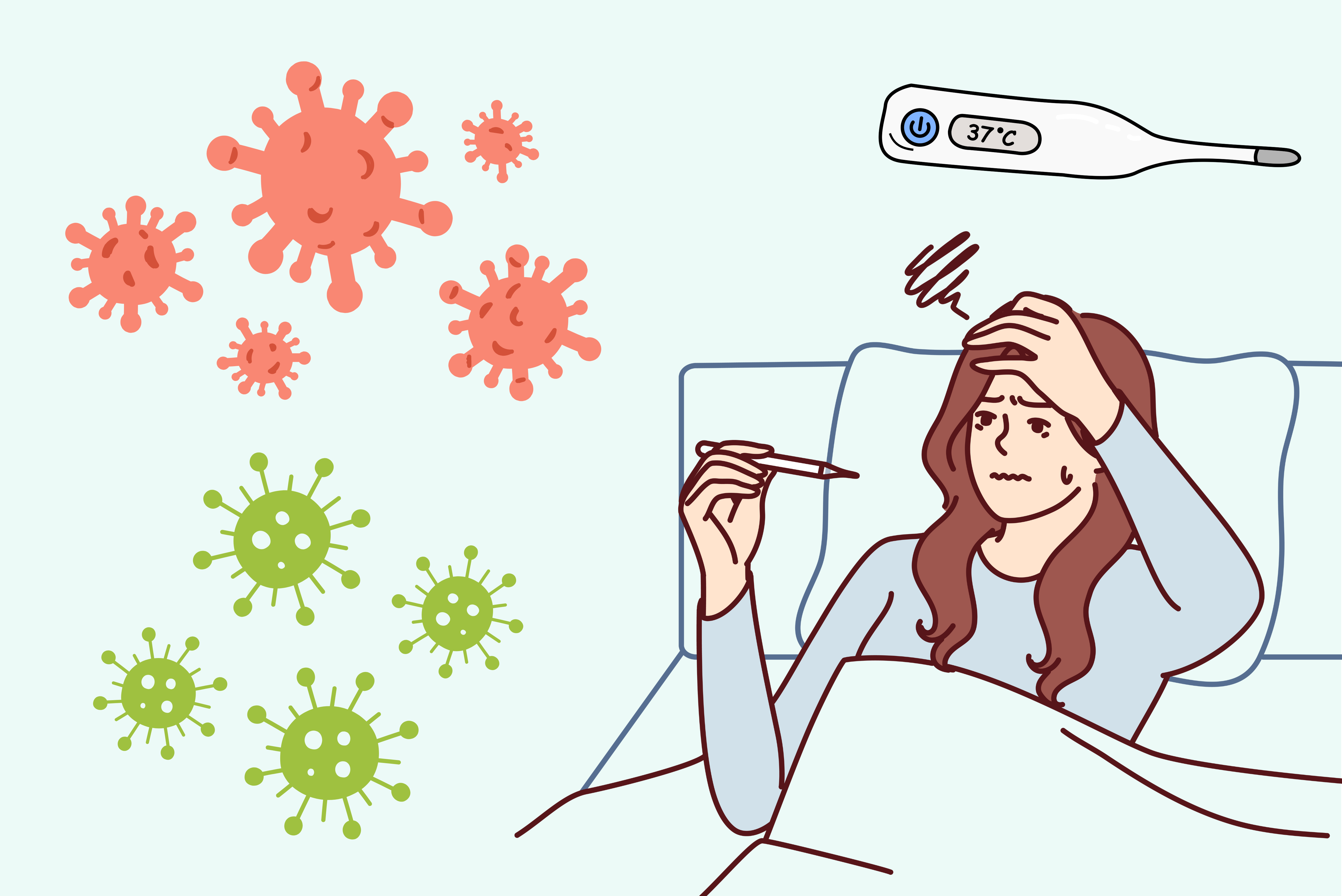
よくご覧いただいているページ